
スタートアップ連携で太陽光発電の既存事業をバリューアップ!
オープンイノベーションの成功事例をご紹介
~Plug and Play Japan×東京センチュリー~
2025年2月20日
DX戦略を加速させるために必要不可欠なスタートアップとの連携。前回の記事では、オープンイノベーションをテーマにPlug and Play Japan(以下、PnPJ)の荒井さま・大村さまと東京センチュリー(以下、TC) DX戦略部 の高野さんの対談をお届けしました。
連載後編となる本記事では、スタートアップ企業との協業により既存事業をバリューアップし、オープンイノベーションが創出された好事例をご紹介します。TCの連結子会社が管理する熊本県荒尾市の太陽光発電所は、蓄電池を併設したことで以前より無駄なく効率的に発電・売電ができるようになりました。運営における課題と解決までの経緯やスタートアップ企業との関係構築などについて、TCの渋谷さんと小宮さんにお聞きしました。
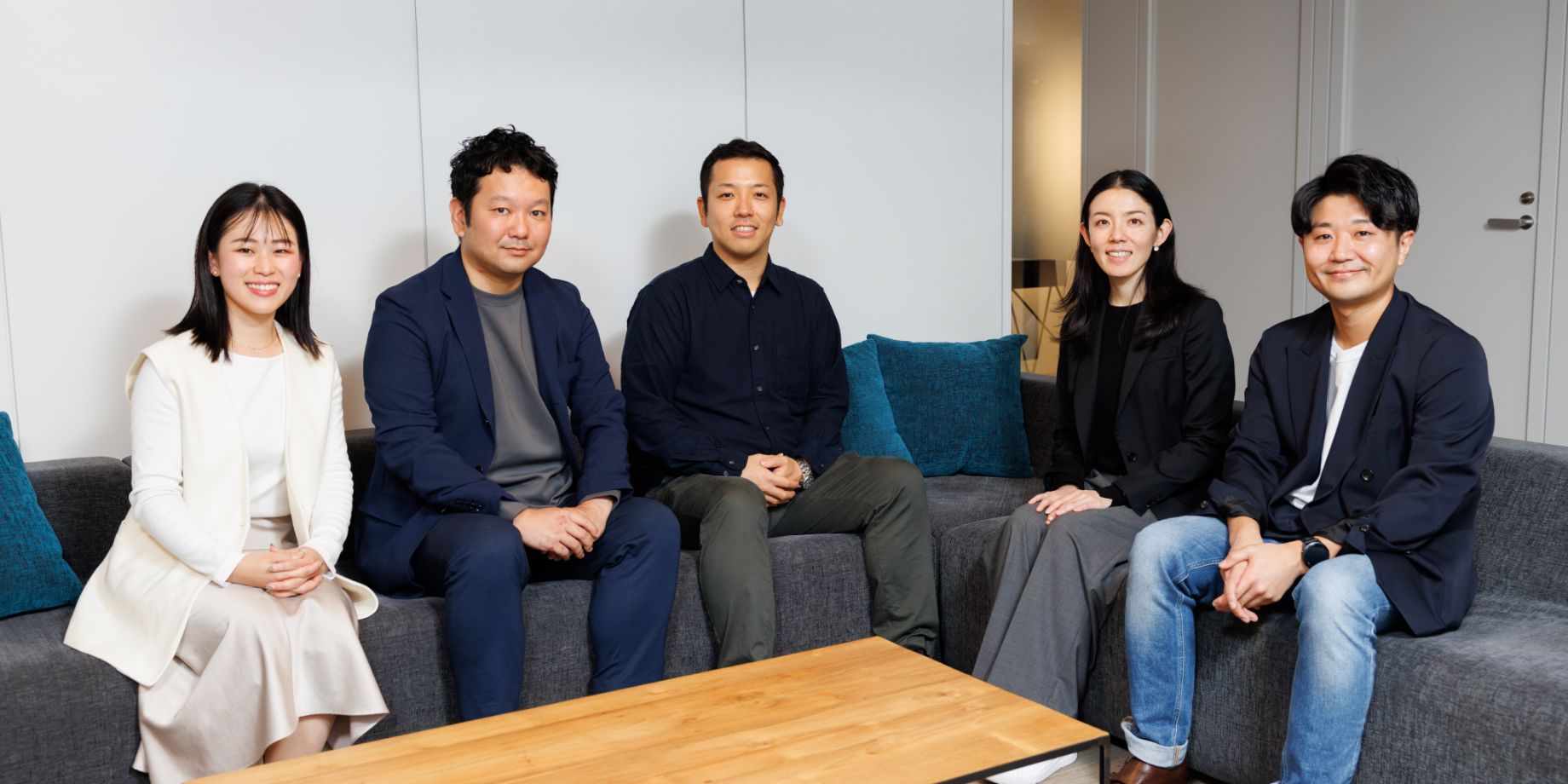
左から、TC 小宮さん・渋谷さん・高野さん、PnPJ 大村さま・荒井さま
スタートアップ連携でFIP転+蓄電池併設を実現
――Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムを通じて出会ったスタートアップ企業との協業により、既存事業をバリューアップするオープンイノベーションの好事例が生まれたとお聞きしました。まずは、そのスタートアップ企業について教えてください。
渋谷:Tensor Energy株式会社(テンサーエナジー、以下「Tensor」)というスタートアップ企業になります。再生可能エネルギーの発電事業を行う企業向けに「Tensor Cloud(テンサークラウド)」という蓄電池を含めた電力管理や財務管理のクラウドプラットフォームを開発・提供しています。DX戦略部 高野からPnPJのアクセラレータープログラムを通じてご紹介いただき面談を実施、社内承認を経て、協業がスタートしました。
――Tensorさまとの協業内容について教えてください。
小宮:熊本県荒尾市の蓄電池併設型太陽光発電所の運用に関するシステムを提供していただいています。同発電所は2015年から運用されており、2024年6月に蓄電池が併設されました。発電所への蓄電池設置は当社初の案件です。発電所が位置する九州エリアは、日照時間が長く再生可能エネルギーの普及が進んでいることから出力制御(※1)が発生しやすい地域です。春や秋は気候が穏やかで日中の電力消費量が少なくなることから、出力制御(=発電・送電を強制的に停止する)がかかりやすい傾向にあります。
この出力制御は、太陽光発電所において収益を左右する大きな課題でした。これらの課題の解決策に加え、FIT(※2)以外の発電所の開発拡大、FIT終了後の事業運営検討から、熊本県荒尾市の発電所にてFITからFIP(※3)への切り替えと蓄電池の併設を、実証としてスタートしようということになりました。
しかし、FIPは売上が日ごとに変わりますので、予実管理が以前とは比較にならないほど複雑になります。加えて、計画発電量や約定量などを外部機関に事前に提出するなどの作業も発生します。新たな課題への対応を模索する中でTensor社が開発した「Tensor Cloud」が最適なソリューションであると判断し、協業が始まりました。

熊本・荒尾メガソーラー発電所に設置した併設型蓄電池
(※1)電気が需要以上に発電され、余った時に発生する発電制御。近年では、再生可能エネルギーの導入が進んだことにより、需要が少ない時期などには、火力発電の出力の抑制や地域間連系線の活用などにより需給バランスを調整した上で、それでもなお電気が余る恐れがある場合に再生可能エネルギーの出力制御が行われる。とくに春(3月~6月)や秋(9月~11月)は、気候が穏やかになることで空調の使用頻度が下がり、電力需要が減少することから発電量が需要量を上回り、出力制御が集中する傾向にある
(※2)FIT…Feed in Tariff。日本語では「固定価格買い取り制度」と訳される。発電した電力を電力会社が全て固定価格で買い取ることを政府が保証する制度。ただし、発電施設の規模により10年から20年までと、買い取り期間が定められている
(※3)FIP…Feed-in Premium。基準価格にプラスして、市場の変動に応じて「プレミアム」と呼ばれる追加額が買い取り価格に付加される制度。
スタートアップ連携を勝ち取るためのハードルは、懸念点の払拭と熱量で乗り越える
――大企業がスタートアップ企業との協業に至るまでにはさまざまなハードルがありそうですね。経営陣の方々の反応について教えてください。
渋谷:スタートアップ企業は歴史が浅く実績が少ないことに加えて、財務面でのリスクやFIT制度下での安定したキャッシュフローを生み出す事業からキャッシュフローが約束されない事業へ変更するリスクなどは、懸念材料となります。今回の協業について承認を得ることができたのは、FIP制度を導入した太陽光発電所に蓄電池を併設することが全国的にも先駆けとなる事例であること、切り替えによって得られるメリット、そして現場で発生する新たな負担を解決するためのスタートアップ企業の技術を総合的に検討した結果だと思っています。
小宮:Tensorとの協業はPOC(※4)からのスタートでしたが、検討段階で提出していただいたデータの精度が高かったことも大きな後押しになったと思います。数字を用いることで、経営陣の方々にもご安心いただけたのかもしれません。
(※4)POC…Proof of Concept。日本語では「概念実証」と訳される。新たなアイデアの実現可能性や成果を検証するために、プロジェクトを試行すること。

渋谷「スタートアップ企業にしかない技術を求めているので、ぜひその想いをぶつけてきてくれるとうれしいですね」
既存事業のバリューアップでオープンイノベーションを実現
――両社のオープンイノベーションはどのように実現したのでしょうか?
小宮:今回の案件は、以前より運営していた発電所をさらにバリューアップさせる事業となります。まさに先ほどお話のあったとおり(※前編を参照)、ゼロイチではなく、既存事業である発電所における「知」とTensor社の技術開発力の「知」を組み合わせてイノベーションを起こすという、当社としての新しいチャレンジでした。
例えば、電力市場での約定結果後の充放電スケジュールの策定ロジックや、オペレーション漏れを防ぐための設定など、「Tensor Cloud」の新機能開発時に細かい部分まで議論させていただき、ユーザー目線としての意見もくみ入れていただきました。
――オープンイノベーションによる成果をどのように実感していますか?
小宮:一緒に議論を重ねることによって、電力取引の仕組みやシステムに関する新しい知見・ノウハウの蓄積ができたことは、当社としても個人としても非常に財産になりましたし、毎週のミーティングが待ち遠しいほどいつもワクワクしていました。一緒に作り上げていく過程や完成版を実際に使用したときの高揚感は忘れられません。内部だけでは得られない刺激があると、オープンイノベーションの意義を実感しています。本案件で得た知見や経験は、今後の開発にも活かすことができると感じています。

小宮「若い時期からこのような経験ができて良かったです。Tensorさんに出会えたことに感謝しています。」
DX・GXの推進で、企業価値向上を目指す
――オープンイノベーションは、中期経営計画の基本方針でも掲げているGX(グリーントランスフォーメーション)にも大きく関わってくる要素かと思います。
渋谷:TCは中期経営計画2027において、基本方針としてTC Transformation(TCX)を掲げ、主要項目として「GX」・「DX」推進に取り組んでおります。この2つのトランスフォーメーションは「自らを変革し、変化を創造する」というテーマを実現するための両軸です。PnPJの皆さまとのコミュニケーションを通じて、多くのスタートアップ企業がカーボンニュートラルのための対応への技術開発や新たなビジネスモデル構築に注力していることが分かりました。M&Aや出資も検討しながら、長期的な視点で、引き続き環境インフラビジネスにおける成長領域を広げていきたいと思います。
――ありがとうございました。最後に、これからの抱負をお願いします。
渋谷:オープンイノベーションを主管するDX戦略部のメンバーとは月に1回の面談を通じて情報交換をしています。DX戦略部は業務効率化の「守り」と事業拡大の「攻め」という2つの観点からDXを進めるというミッションがあり、環境インフラ事業分野は環境インフラビジネスの領域で社会課題の解決と組織の成長を両立させるというミッションがそれぞれにあります。事業分野ごとの縦割りではなく、全社横断的な仕組みを構築して顧客提供価値の向上を果たしていきたいと思います。PnPJの皆さんとともにスタートアップ企業の方々の動向を注視しながら、既知と既知との融合で、未来に資するイノベーションを生み出してまいります。


渋谷 雄大(しぶや・ゆうだい)
東京センチュリー株式会社 環境インフラ営業統括部 GXビジネス推進室 マネージャー
2021年に中途入社。環境インフラ事業における、事業会社への出資を含むパートナー戦略の企画・運営を担当。

小宮 知佳(こみや・ちか)
東京センチュリー株式会社 環境インフラ第二部 業務管理室
2021年に新卒入社。2024年よりTensor Energy株式会社との協業による太陽光発電所(熊本県荒尾市)の運営・管理業務の主担当を務める。石油類(リチウムイオン蓄電池など含む)の取り扱いが可能な乙種第4類危険物取扱者の資格を保有。
※記事の内容、肩書は掲載当時のものです。
おすすめ記事

〜作りたいのは、安心・安全で誰もが自由な移動を選択できる未来〜
2026年1月28日
東京センチュリーの事業の核となっているの…

オープンイノベーションの成功事例をご紹介
~Plug and Play Japan×東京センチュリー~
2025年2月20日
DX戦略を加速させるために必要不可欠なス…
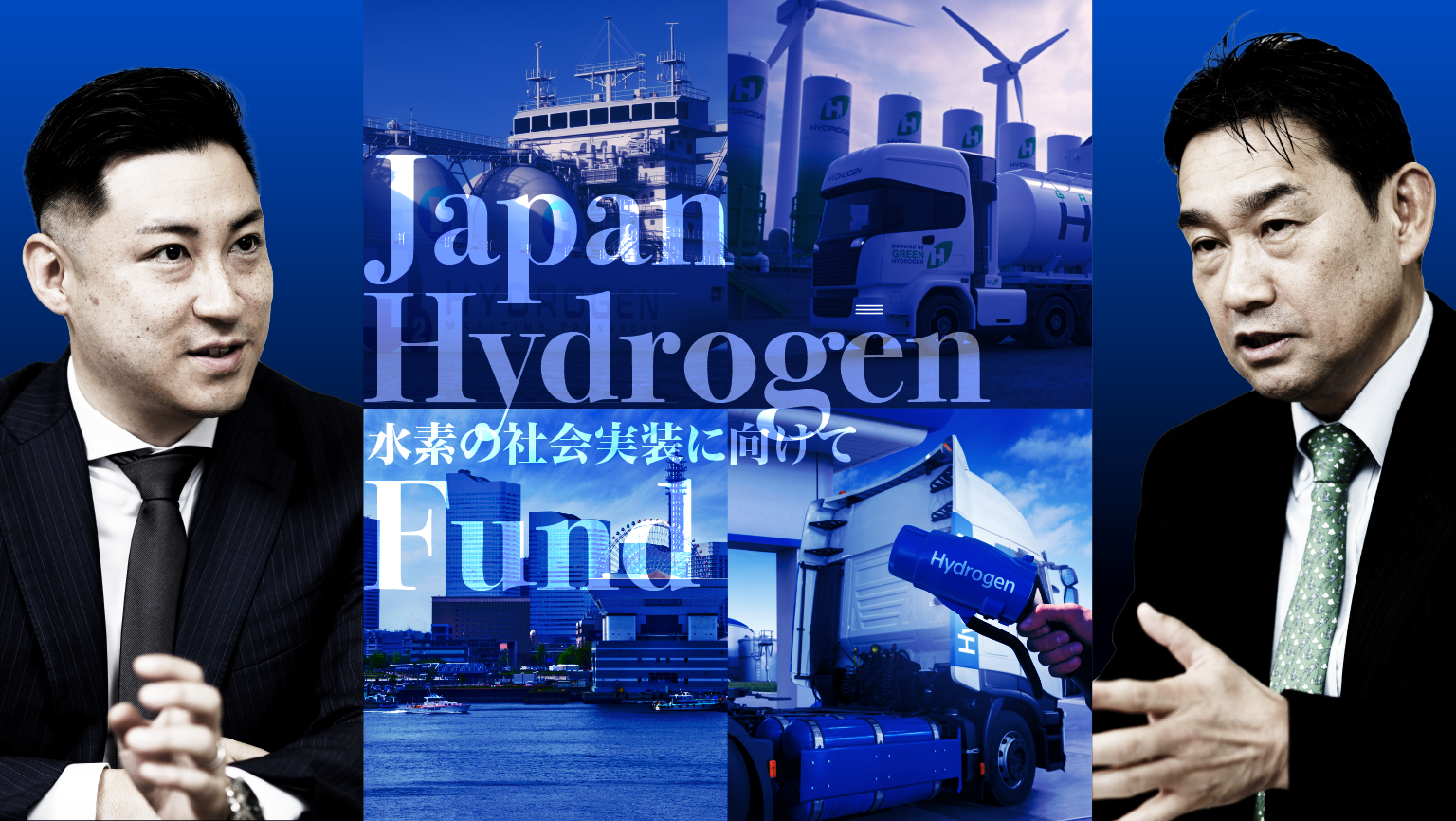
2025年2月14日
次世代エネルギーとしての活用が期待されて…



